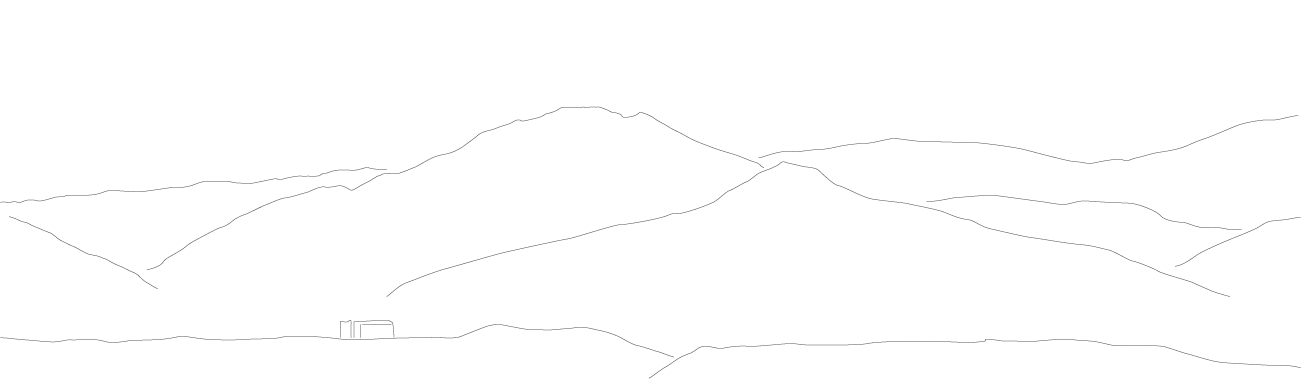News
新着情報
ときどきの信州飯田
百万本のコスモス
信州飯田は南と中央の二つのアルプスの間の伊那盆地に位置し、諏訪湖に端を発する天竜川は盆地を太平洋に向かって南下します。でも信州飯田から国道153号線を南下すると愛知県境に向けてどんどん標高は上がってゆきます。
標高1,189m治部坂峠(じぶざかとうげ)は長野県最南端のスキー場でもあります。9月中旬はこの広大なスキー場が百万本ものコスモスで覆われます。現地でお聞きすると今年のコスモスは2m越しでとても背が高いとのこと。今年は真夏の雨が多かった。帰省客で賑わうお盆も多雨でした。異様に伸びた地域の雑草や社内の緑地の雑草と戦ったつもりの私にはコスモスの伸びが良いことは然もありなんという気分です。それにしても見事なスケールのコスモスです。
加えて、ここ阿智村は”星が美しく見える村”として有名です。宇宙にはこんなにたくさんの星が存在したなんて。”星空の明るさ”を体感してほしい。そんな田舎です。
〈上〉長野県下伊那郡阿智村浪合(飯田中心市街地から車で40分)治部坂高原スキー場にて
上段の今年の見頃は9月10日前後でしょうか 撮影日 2022.9.17
〈下〉長野県下伊那郡阿智村浪合 治部坂高原スキー場にて
リフトで上部まで上がって散策が出来ます 撮影日 2022.9.17
飯田りんごん直前の中止でもって不動滝
アルプスの残雪も僅か谷筋だけとなっていよいよ新緑の季節となりました。飯田市のシンボル風越山は淡い緑に覆われます。濃い 緑と混在すると余計に淡さが引き立つようです。天竜川左岸から当社「アイス信州飯田工場」越しの遠望でも新緑の淡さがよく見て取れます。
2022年8月6日(土曜日)に予定されていた飯田りんごん(信州飯田の夏祭り)と日本最大と言われるいいだ人形劇フェスタ2022がコロナにより直前に中止が決まりました。残念です。当社スタッフも同日開催で一年に一日だけ生シロップのかき氷を飯田の地元の皆様に目の前で作って食べていただく機会を失ってしまいました。楽しみにしておられた皆様申し訳ありません。来年こそはお会いしましょう。
でもって、8/6は取材の矛先を変えて中央アルプスの前衛の山、大島山の山懐にある「不動滝」(下伊那郡高森町)を何十年ぶりに訪ねてつかの間の涼を感じてまいりました。信州飯田の市街地からわずか30分弱ですが標高は1,096m。緑の日陰ををくぐってきた冷涼で湿り気を含んだ空気と大島川の沢の流れの音は臨場感ある別天地です。滝の落差は50mとなかなかのスケールです。
ここへ向かう林道を見て気が付きました。両脇の下草がきれいに刈られており車を走らせてもとても気持ちがいいのです。この一帯は恐らく財産区とか保安林とか呼ばれる膨大なスケールの山林の一角です。こうした手入れをするというのは地球に直接注射針を刺すような些細な行動かもしれませんが高温多湿な日本において里山の手入れは長い目で見るととても重要なことです。頭が下がる思いです。最初の一台目だった私の後に何台か車が上がってきました。別天地をちゃ
んと知っているのですね。
〈上・下〉不動滝(下伊那郡高森町牛牧) 撮影日 2022.8.6
信州飯田の淡い緑
アルプスの残雪も僅か谷筋だけとなっていよいよ新緑の季節となりました。飯田市のシンボル風越山は淡い緑に覆われます。濃い 緑と混在すると余計に淡さが引き立つようです。天竜川左岸から当社「アイス信州飯田工場」越しの遠望でも新緑の淡さがよく見て取れます。
環境省百名水の猿庫の泉はこの風越山の山懐にあります。紅葉の猿庫もいいですが新緑はまた格別です。茶の湯に向いたと言われる所以は軟水つまり溶け出したものが少ない水に特徴があります。溶け出したものが多いつまり硬水である大陸の大河とは対極の水の性格です。この軟水文化がお茶や出汁や日本人の味覚のベースとなっています。
今でも岡崎に現存する宗徧流の不蔵庵龍渓(1842没)宗匠がお茶に向いた水を求めてここに辿り着いたとされています。pH計などあり得ない時代に舌ひとつでいい水を探り当て、それが今日の科学でも裏付けられるという。そんな江戸時代のお話を現代のお父さんが子供に聞かせるというスタイルで昭和20年代の国語の国定教科書に「いずみを求めて」というタイトルで取り上げられ、この猿庫の泉が全国に知られることとなったようです。
一帯は砂地の山。如何にもすっと真っ直ぐな檜が育ちそうな山肌です。その水はまろやかで清々しさが少し湿り気を帯びた澄んだ空気とともに鼻を抜けてゆきます。春から秋口まで週末は猿庫保存会の皆様による野点も行われています。どうぞお訪ね下さい。
〈上〉飯田市下久堅知久平から当社工場(左下)越しに風越山(標高1,535m)を望む
撮影日 2022.5.3
〈下〉飯田市 風越山山麓 猿庫の泉 撮影日 2022.6.14
七年ぶりの飯田お練り祭り&桜
七年に一回開催される信州飯田のお練り祭り。今年は3月25日(金)より三日間。今年は諏訪の御柱(日本三大奇祭)飯田のお練りとコロナで1年遅れの善光寺のご開帳とが同じ年に開催されることとなり信州の今年の春の賑わいは特別なものとなっています。今回のお練り祭りは三十六ものこの地域の伝統芸能の晴れ舞台は見応えがあります。
とりわけの華は大名行列と東野の大獅子でしょうか。獅子頭だけでも30キログラムもあり役を担う人(頭)は20名編成で数十秒で交代してゆきます。この大獅子を3日間やるためにはお囃子を含めて総勢230名もの人材を擁します。練習に明け暮れて迎える本番への気合いの入り方はただならぬものを感じます。
当社の天然氷時代の氷造りの発祥の地、飯田市北方(旧伊賀良村)にも立派な獅子舞があります。今回も所望に応えて当社本社前で舞をご披露下さいました。ありがとうございました。
七年という時には重みがあります。七年前はどんなだったろう。七年後はどんな自分やどんな時代になっているだろう。七年後にはリニア中央新幹線が開通してますよね!という気の早い話も出てくるそんなお練り祭りでした。
ゆっくりお花見もままならぬこの春、美しい一本桜に出会えました。増泉寺(飯田市大瀬木)の垂れ桜です。中庭の中央に鎮座するシーメントリーで静的な美しさ、それに風が加わるとしなやかで動的な味わいもあります。
〈上〉信州飯田 中心市街地 通り町 当社本社近くにて お練りの華のひとつ 東野大獅子
撮影日 2022.3.26
〈下〉増泉寺の垂れ桜 飯田市大瀬木(中心市街地から10分) 撮影日 2022.4.3
南アルプスの三千メートル峰九座
南アルプスには九座の三千メートル峰があります。北は仙丈ガ岳に始まり南は日本の三千メートルの最南端の聖岳で終わる九座です。信州飯田からはちょっと小高いところに上がればすべて見えます。二月下旬まで寒さが全く緩まず峰々の白さが引き立つ今年の冬です。
当社では現在地下水の環境や構造を専門家にお願いをして再調査を進めています。この伊那谷中央部の地下250メートルという深層へと辿り着いた私たちが使わせていただいている天然水は一体どのような地球の営みから生まれてくるのか。調査によると今から300年ほど前にこの伊那谷(中央アルプス系)に降った雪や雨がそんな長い年月をかけて深い深い地下に蓄えられた水だそうです。全国有数の花崗岩の基盤の上に水を蓄える層(帯水層)と鉄板のように水を通しにくい層(不透水層)とが何層かに重なり豊かな水を蓄えているようです。誰も行ってみたことのない地球内部の種明かしの進展にわくわくするものがあります。
42年前に二年間に渡る水選びからこの地下水にたどり着く段階でおよその見当はついておりましたが今日の科学のお陰でより推測の精度があがり、まずもって貴重克つ氷作りの適性度も高い水との出会いにリアル感が増し、改めて感謝の気持ちもひとしおです。我々人類が望んでも自らは作れない大地の贈り物それが水であり土なのだとつくづく思います。
〈上〉飯田市久米(中心市街地から15分)久米ヶ城城址公園 海抜722m 展望台から 南アル
プスを望む 中央は天竜川 写真の左が上流(諏訪湖方面)撮影日 2022.2.26
〈下〉同久米ヶ城城址公園 展望台から 南アルプスを南部 赤石岳 聖岳を望む
赤い橋付近は時又の街(天竜船下りの港)撮影日 2022.2.26
2022年 令和四年 明けましておめでとうございます
あけましておめでとうございます。平素のご厚情に心より感謝申し上げます。
皆様におかれましては今年がどうぞお健やかでご発展の一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
また世界全体でコロナというこの困難を克服できますよう、弊社も地道な行動を積み重ね食品企業として適切な責任を果たして参ります。
新たな一年どうぞよろしくお願い申し上げます。
〈上〉信州飯田から望む南アルプス方面からのご来光
方向としては南アルプスの易老岳と光岳の中間あたり。樹木の様子からして重なり合ってはいますがこのシルエットは南アルプスより随分手前の伊那山地の一部と思われます
撮影地 飯田市北方 日本トレッキング付近より 撮影日 2021.12.20 7:18
〈下〉信州飯田から望む南アルプス方面からのご来光 まさに伊那谷に新しい光が当たり始める瞬間です撮影地 飯田市北方 日本トレッキング付近より 撮影日 2021.12.20 7:18
天然氷時代の氷屋
弊社は明治33年、西暦に直すと分かりやすいのですが1900年に長野県飯田市の西の山麓(旧伊賀良村)に天然氷の氷屋として創業し、中心市街地(現在の通り町営業所)に販売拠点をもって始まりました。
氷屋は夏の需要ピークのブレが年毎に大きく悩ましいものがあります。冬造って氷室に蓄えて夏に売るという天然氷から電気と冷凍機で作る氷(当時はそれを人造氷と呼んだそうです不思議な響きの言葉です)に切り替えたのは昭和33年のことでした。
天然氷時代は冬に蓄えた量しか次の夏に売る氷がないわけです。猛暑の夏にはどうやって対応したのだろうと想像します。当時の二つの氷室(氷倉)の在庫がなくなりそうな猛暑の夏は氷を持っている氷屋さんから分けてもらうしかなく長野県では最も標高の高い立地の富士見町の同業に分けていただいた夏もあると先代から聞きました。(輸送手段は貨車)猛暑の夏はさぞ儲かったのかというと仕入氷はどうしても高くつき売上げに比例する利益は出ない、時には逆ざやもあったそうな。
一年の天候や吉凶を占う諏訪湖の御神渡り(おみわたり)は湖の全面結氷から湖面の氷 が膨張でせり上がる自然現象です。550年前の室町時代から一年も欠かすことなく記録をとり続けられてきた学術的にも価値ある記録だそうです。1990年以降は31年間で出現は僅か9回。温暖化の影響と思われます。
今年の冬、暮れから低温傾向が緩むことなく続いており御神渡りの出現が期待されます。ここ2年続いた超暖冬の後の夏は不順でした。今回の冬らしい冬のあとはどんな夏となりますでしょうか?
長野県下伊那郡松川町 池ノ平湖の結氷(飯田市中心市街地から25分)背景は中央アルプス南部
海抜802m 撮影日 2022.1.9(氷屋さんの氷とは無関係です)
べっぴんさんのハナノキ
一本の樹にいったい何枚の葉があるのだろうか。べっぴんさんの葉を撮ろうと落ち葉を探してみるとこれが一枚一枚皆違う。一枚一枚が人の顔のように見えてくる。色・形・大きさを選んで、洗濯ばさみで固定して逆光に翳してモデルになってもらった。
飯田市中心市街地から車で10分の山本二ツ山の堂坂稲荷のハナノキは単独木。この秋の暖かさで紅葉は一週間程遅い。ハナノキの落葉は音に喩えると”はらはら”ではなく一晩で“ドサッ”と言う感じ。その赤い色は土目の影響なのか土地土地で全く趣の異なる紅色となる。中でもこの樹の紅色は格別。私は好きです。
実は当社の食品部門の屋号「東山道」のテーマカラーはこのハナノキの赤なのです。食欲をそそる赤。そして、このハナノキの自生地と東山道の要衝恵那山の神坂峠(長野県境)が一致することから“東山道の赤”となりました。
〈上〉撮影 2021年11月3日 長野県飯田市山本二ツ山 堂坂稲荷のハナノキ
べっぴんさん落ち葉を拾い集めてみた
〈下〉撮影 2021年11月3日 堂坂稲荷のハナノキ 暖かい秋で遅い紅葉は八分程度
県境根羽村の初秋
長野県と愛知県境に茶臼山(1,415m愛知県最高峰)があります。コスモスが終わり紅葉直前の10月上旬ってちょっと花が少ない時期です。地元紙によると茶臼山下のカエル館近くにウメバチソウが咲いているとのことで県境の根羽村を目指しました。飯田市街から65分。
まずはカエル館(茶臼山高原両生類研究所)に立ち寄りました。同じ長野県なのに飯田から来る人は珍しいそうで殆どは愛知県民。カエル館名物”ワンと鳴くネバタゴガエル”に会いました。5月の求愛時期に頻繁に鳴くとのことで諦めていたらなんとその美声を聞くことが叶いました。スピッツやポメ系の美声ですね。驚きです。ウメバチソウならあそこだよと熊谷館長が教えて下さいました。
辺り一面真っ白を連想して行ってみると畳一畳にひとつくらいの直径約2cmの可憐な佇まいでした。
折角の根羽村なので“月瀬の大杉”も訪ねました。長野県一の巨木は樹高40m。当社の立体自動倉庫が20m。並の広角レンズには収まりません。大きな木に抱かれることに古来から尊厳や畏敬を感ずる日本人。私もそんな一人なのでしょうか。
古い火山の痕跡があったり、不思議なカエルに出会えたり、亜高山帯の可憐なウメバチソウに出会えたり、巨木に圧倒されたり、県境根羽村はなかなか面白いところでした。
〈上〉撮影 2021年10月2日 ウメバチソウ(ユキノシタ科)
長野県根羽村 カエル館近く茶臼湖にて
〈下〉撮影 2021年10月2日 月瀬の大杉 樹高40m
長野県一の巨木 長野県根羽村月瀬
信州飯田の水瓶
飯田市民の水瓶は両アルプスの恩恵からいくつもの水源があります。最も規模が大きく多くの飲み水や豊かな農業を支えているのがここ飯田松川の松川ダムです。昭和49年に松川ダムが完成したことで昭和三十六年のこの地方の大水害を再び繰り返さない水のコントロールも可能となりました。
今年の信州の梅雨明けは早めの7月16日でした。が、まさかその後にもう一度梅雨のような長雨がやってくるとはだれも思いませんでした。全国の被害に遭われた地域の早い復旧をお祈り申し上げます。
弊社のような夏商品の売れる三要素。①天候 ②時間(学校や会社が夏休み)③お金(ちゃんとボーナスがでる)肝心なのはそれらが揃って来てくれることです。普通の夏なら梅雨明けから一ヶ月はお盆もからんでその条件をすべて満たしてくれるのですが。陽気だけ後からやって来たとかではお客様の心に火がつかないものなのです。あくまでもセットで来てほしい。そんなやからにコロナ渦と長雨。
コロナの波の向う側が早く見えてきてほしい。唯々それを祈るばかりです。
〈上〉撮影 2021年8月29日 飯田市上飯田 松川ダム放水路
〈下〉撮影 2021年8月29日 飯田市上飯田 松川ダム